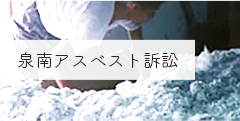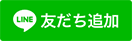造船アスベスト国賠大阪訴訟で原告弁護団が意見陳述
2025.05.052023(令和5)年2月に提訴した造船アスベスト国賠大阪訴訟は、大阪地方裁判所第23民事部(齋藤毅裁判長)に係属しています。2025(令和7)年4月25日の期日では、鎌田幸夫弁護士が、本件の争点と原告らの主張をまとめた意見陳述を行いました。
1 まず、国の規制権限不行使の違法の考え方について述べます。
本件では、労働者等の生命健康を保護法益とする労働行政分野における規制権限行使のあり方が問題となっており、国の責任を肯定した炭鉱の筑豊じん肺、石綿工場の泉南アスベスト、建設現場の建設アスベスト訴訟の各最高裁判決が先例となります。最高裁判決によれば、国には、できる限り速やかに、適時にかつ適切に規制権限を行使することが求められるのであって、労働大臣の判断の専門性や広い裁量があるとする国の主張は誤っています。その他、本件における国の様々な主張は、泉南訴訟、建設訴訟において国が繰り返し主張してきたことと全く同じですが、いずれも排斥されて国の責任が肯定されています。
また、本件で、国は、造船業界では大手造船会社を中心に安全配慮義務が履行されていたと強調し、国の責任が第二次的かつ補完的責任であるとして、国の責任を否定ないし限定しようとしています。しかし、事業者の安全配慮義務違反の責任と国の規制権限不行使の違法の責任とは根拠も要件も異なり、国の責任は事業者の責任とは別個独立の責任です。加えて、石綿肺、肺がん、悪性中皮腫等の石綿関連疾患は、ばく露から発症までの潜伏期間が長く、事業者や労働者がその危険性を把握することは困難な反面、国は危険性情報を独占していました。そのため、国が適切に規制しないと、効率を優先する事業者による安全配慮義務や石綿の危険性を全く知らされていない労働者らの自己責任に委ねていては、アスベスト被害の発生拡大を防止できなかったのです。このような石綿による被害と加害の構造は、炭鉱でも、石綿工場でも、建設現場でも同じであり、我が国の産業社会に共通するのであって、ひとり造船現場のみが異なることなどあり得ません。
2 次に、造船現場におけるアスベスト被害の危険性と国の認識ないし予見可能性について述べます。
海外では、1930年代から造船現場でのアスベスト被害が報告され、とりわけイギリスでは、建設業に先んじて1960(昭和35)年に造船アスベスト規制がなされました。国内でも、昭和40年代前半から昭和50年にかけて、造船現場において石綿肺を含むじん肺が多数かつ高率(概ね10~30%)で発生し、1971(昭和46)年当時のじん肺有所見者数は約1000人にも上っていました。国は、1960(昭和35)年から始まったじん肺健康診断結果を通じてこれを把握していたのです。また、国は、昭和30年代の前半頃から、米海軍横須賀基地において雇用者ないし地位協定締結者として造船作業者のアスベスト被害及びその対策の必要性を認識していました。これらの事実からすれば、1971(昭和46)年には、国は、造船現場における深刻な被害の発生を認識していたといえ、筑豊じん肺、泉南アスベストの事案と同様に、直ちに規制権限を行使すべきでした。
仮に、当時において、すでに深刻な被害が発生しているとまではいえなかったとしても、1971(昭和46)年、遅くとも1973(昭和48)年、どんなに遅くとも1975(昭和50)年10月1日には、造船作業者に石綿関連疾患に罹患する広範かつ重大な危険が生じていたものといえます。
というのも、まず、造船業界における石綿関連疾患の労災保険法、石綿救済法による支給決定件数は建設業界に次いで多く、2007(平成19)年度から2022(令和4)年度までの累計数は2005件にも及んでおり、広範かつ重大な被害が現在に至るまで発生し続けています。このことは、石綿関連疾患の潜伏期間が30~40年であることを考慮すると、まさに昭和40年代から50年代以降にかけて、造船現場に広範かつ重大な被害を発生させ得るだけの危険が客観的に存在していたことを示しています。
また、船舶には、SOLAS条約を履行するため船舶安全法、防火構造規程によって不燃材、耐火材の使用を義務付けられ、多種多様な石綿製品が使用されました。このことは、造船便覧や日本海事協会の承認例などからも明かです。造船現場では、このような多種多様な石綿製品を切断、加工する多数の職種・作業があり、作業環境は屋内作業場と同視できる密閉空間で、かつ、混在作業も日常的に行われていました。他方で、石綿に関する安全教育は全くといってよいほどなされておらず、周辺作業者を含めて防じんマスクの着用が徹底されているとは到底いえませんでした。このような状況の中で造船作業者は、直接的ないし間接的に石綿粉じんに曝露し、石綿関連疾患を発症する危険性に晒されていました。
国は、労基署による監督などを通じて、この危険性を認識しないし認識し得ました。さらに、造船現場の濃度測定を行えば、造船作業者が当時の抑制濃度(5本/㎤)を超える石綿粉じんに晒されている可能性があることを認識できたはずであり、広範かつ重大な危険を把握できたというべきです。したがって、国は、建設現場と同様に、むしろ建設現場よりも早い時期に、警告表示(掲示)や防じんマスクの着用義務づけなど造船現場でのアスベスト被害を防止するための規制や対策の強化を行うべきだったのです。
2025(令和7)年2月28日の横浜地裁判決は、屋内作業と評価し得る木艤装職にも広範かつ重大な危険が発生していたことを把握できたとして、造船アスベスト被害について国の責任を肯定しました。このことは屋内作業と評価しうる造船作業一般に同様に当てはまるというべきです。
私たちにご相談下さい。
アスベスト被害に関するご相談は無料です。
アスベスト被害ホットライン
0120-966-329
(平日の10時~18時)
折り返し、
弁護士が直接ご連絡します。
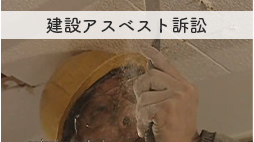
- 私たちは建設アスベスト訴訟を提起・追行し、最高裁で賠償・救済を勝ち取りました。
- 詳しく見る >